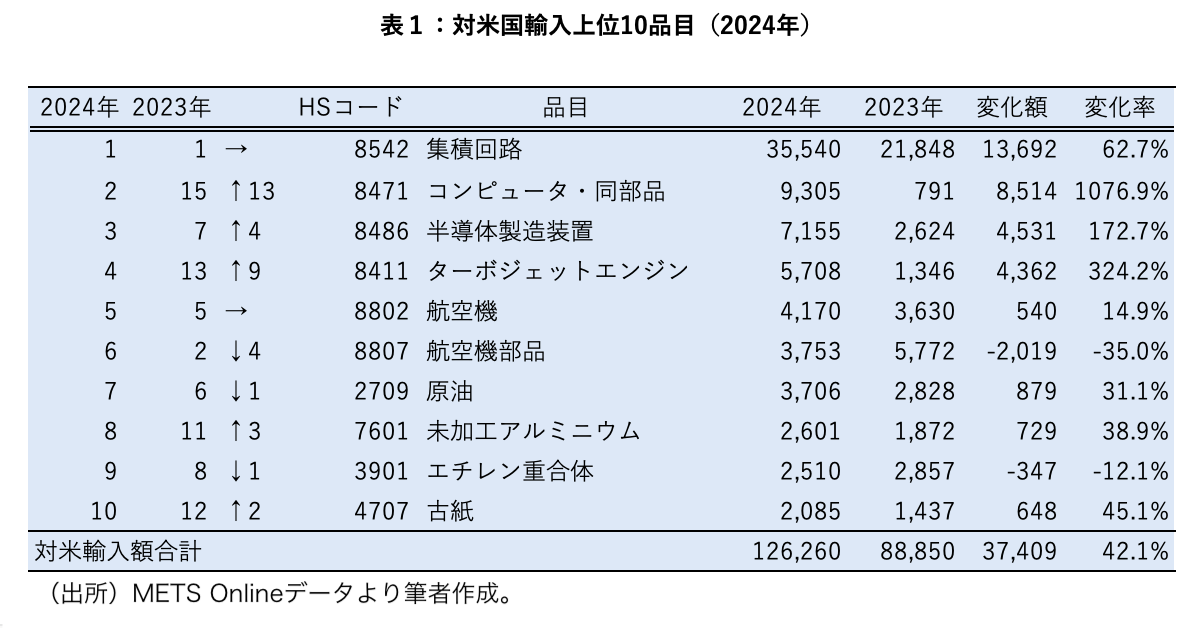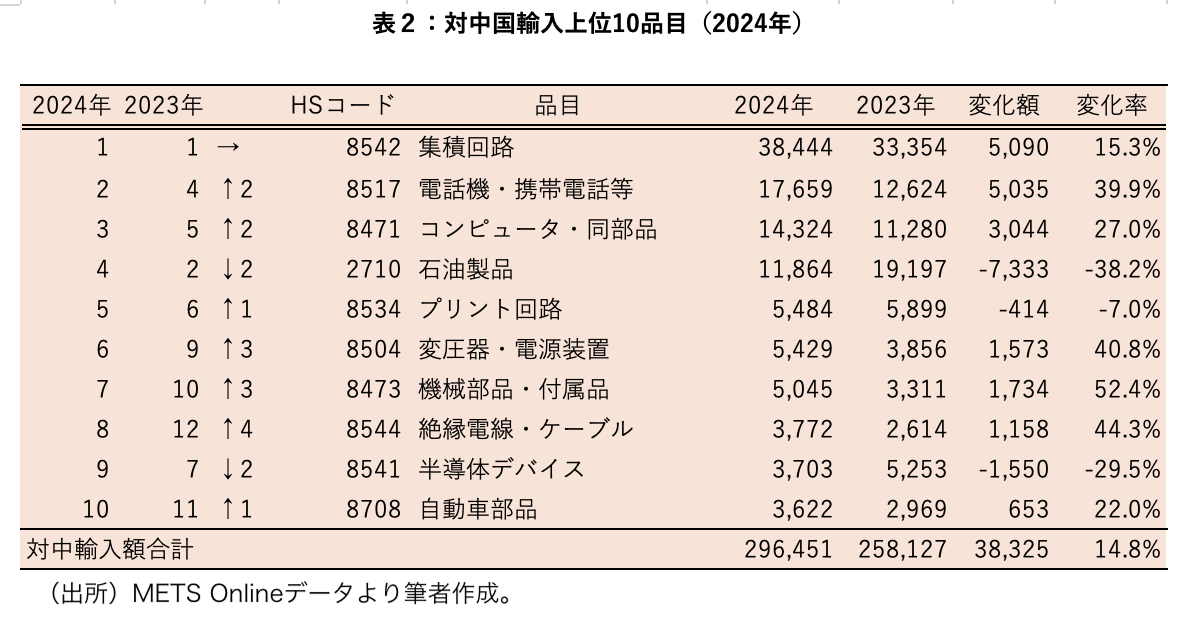Deliver your own message
★マネジメントコミュニケーション
今年に入って、新しい研修コースを始めました。「マネジメントコミュニケーション」というタイトルです。口頭でのコミュニケーションが希薄化していくビジネスシーンの中で、改めて、口頭によるコミュニケーションの大切さを学ぶと同時に、実践力を身につけることを目的とした研修です。
特にコロナ以降、ニューノーマルという生活習慣が定着し、会うよりも会わない、話すよりもメールでという選択が中心となり、仕事の進め方も、随分と変わってしまいました。だからこそ、「直接話すことが大切なんです」と強調することが求められる時代といえます。
★コミュニケーションの4原則
ピータードラッカーは、以下の4つの原則を持ってコミュニケーションは成立すると述べています。
原則1:コミュニケーションとは知覚である
原則2:コミュニケーションとは期待である
原則3:コミュニケーションとは要望である
原則4:コミュニケーションは情報ではない
平たくいえば、相手に意図や真意を伝えようとしない行動はコミュニケーションとはいえないということです。
★説得を嫌がる時代と感動の復活
筆者は研修でロールプレイを多用するのですが、最近は説得を嫌がる人材が増えました。そのため、流れに任されるままに仕事が進んでしまっている傾向があります。
その原因は、期待や要望についてのコミュニケーションの取り方次第で流れが変わる結果に影響を及ぼすという実体験が乏しいことも影響しています。
言葉から受ける感動を取り戻すことで、人間の強さを呼び覚ますことが可能となるのです。
湯浅忠雄の仕事の実績はこちらのWEBサイトより → https://yuasatadao.com/about-us/presidents-greeting/
| 湯浅 忠雄(ゆあさ ただお) アジアで10年以上に亘って、日系企業で働く現地社員向けのトレーニングを行う。「報連相」「マネジメント」(特に部下の指導方法)、5S、営業というテーマを得意として、各企業の現地社員育成に貢献。シンガポールPHP研究所の支配人を10年つとめた後、人財育成カンパニー、HOWZ INTERNATIONALを立ち上げる。 【この記事の問い合わせは】yuasatadao★gmail.com(★を@に変更ください) |