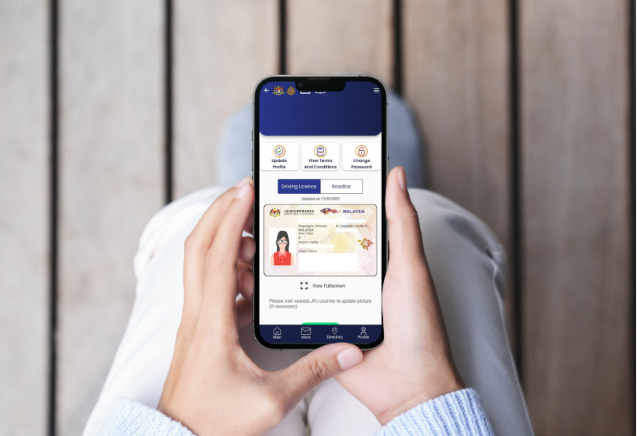It has just begun
★海外に向く人向かない人
4月からマレーシアで新生活を始めた日本人の方々も多いことと存じます。
新天地でのご活躍を祈願するとともに、本稿では、海外に向く人、向かない人について考察をします。
まず、昭和55年版の書籍『現代 プロの条件』(日本経済新聞社編)に記載されていた「海外派遣者としてふさわしくない人」について紹介します。
1消極的な人
2精神面も含め、健康でない人
3自己抑制ができない人
4意志表示がうまくできない人
5単能的な人
6協調性に欠ける
7現地に融和できない
8奥さんに主人と一緒に働く意識のない人
★OKYよりもOKD
以上8点共通する視点は、海外では常に解決策を求められると云うことです。できない理由ではなく、できる方法を考えることは、本人と家族を含めたサバイバルにも関わります。
OKYとは、お前(本社)が来てやってみろという言葉は、愚痴として言いたくなる気持ちはわかります。
一方で、本社に頼らない、あるいは頼る必要のない自律した仕事の仕方は、常に求められます。
むしろ OKD 、お前が来なくても大丈夫だ、の方が頼もしい姿です。
★ロケットスタートのススメ
よく「半年ぐらい様子をみてから本格始動」という言葉を聞くことがあります。しかし、それでは間に合いません。
まず、最初の半年に、徹底して仕事に打ちこみ成果を見せないといけません。
現地社員は、新しい日本人の姿を見ています。その中で、最初にスロースタートを見せると、軽視されがちです。
従って、赴任日を帰任日、就職した日を最終日とあえてみなし、24時間、臨戦体勢で仕事に打ち込むことで現地社員の信頼を勝ち取ってください。
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
湯浅忠雄の仕事です→ https://yuasatadao.com/
| 湯浅 忠雄(ゆあさ ただお) アジアで10年以上に亘って、日系企業で働く現地社員向けのトレーニングを行う。「報連相」「マネジメント」(特に部下の指導方法)、5S、営業というテーマを得意として、各企業の現地社員育成に貢献。シンガポールPHP研究所の支配人を10年つとめた後、人財育成カンパニー、HOWZ INTERNATIONALを立ち上げる。 https://yuasatadao.com/about-us/presidents-greeting/【この記事の問い合わせは】yuasatadao★gmail.com(★を@に変更ください) |