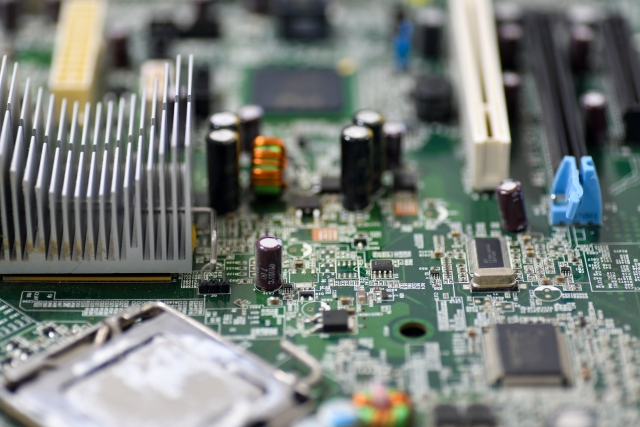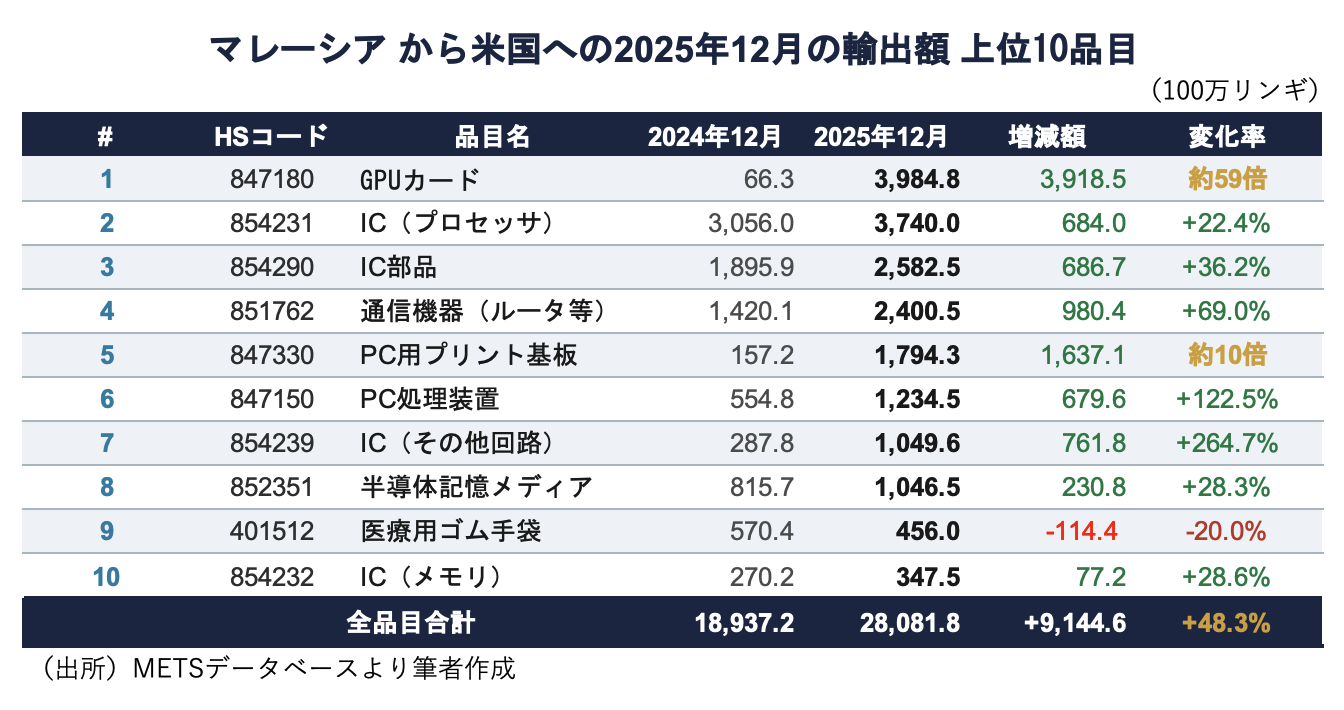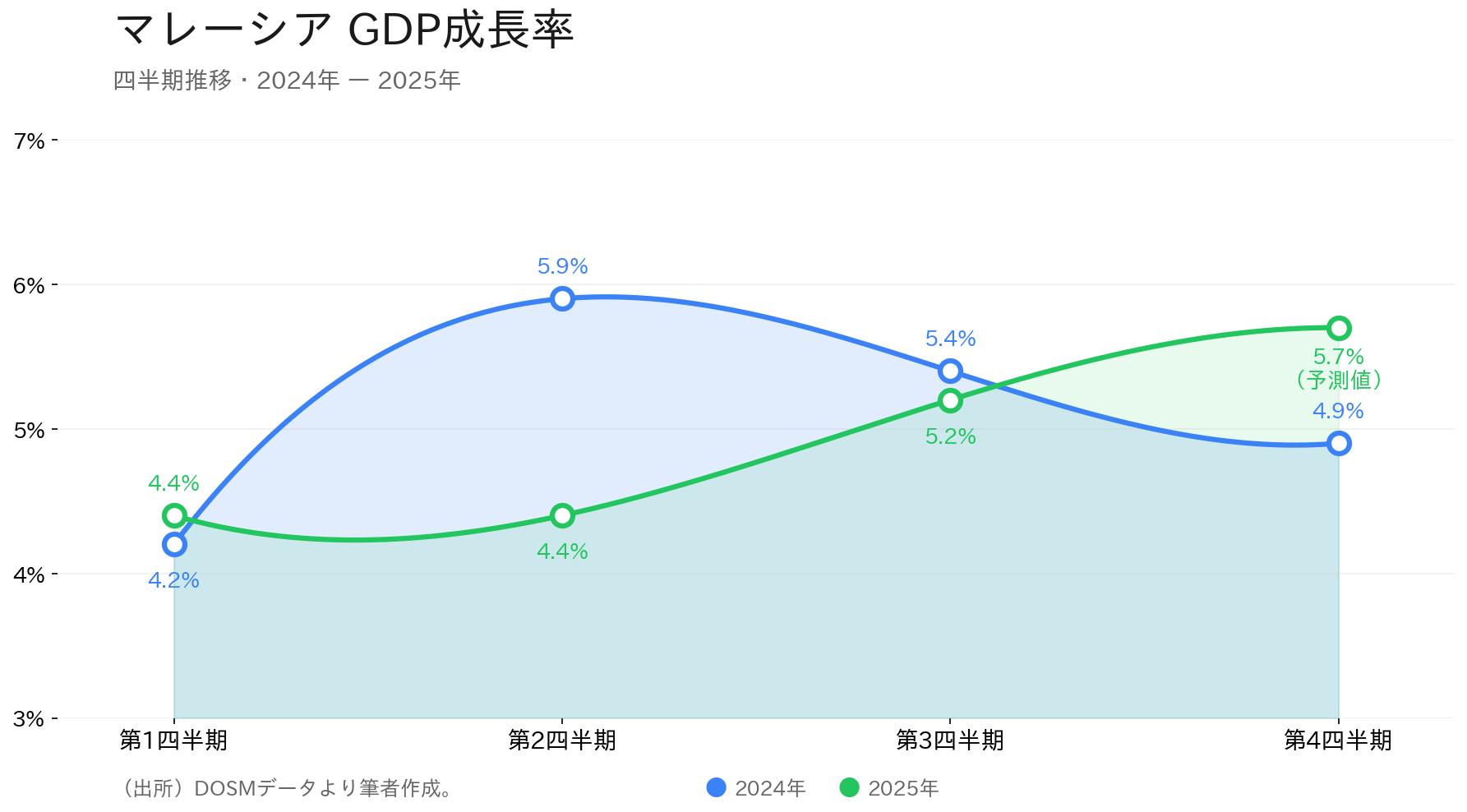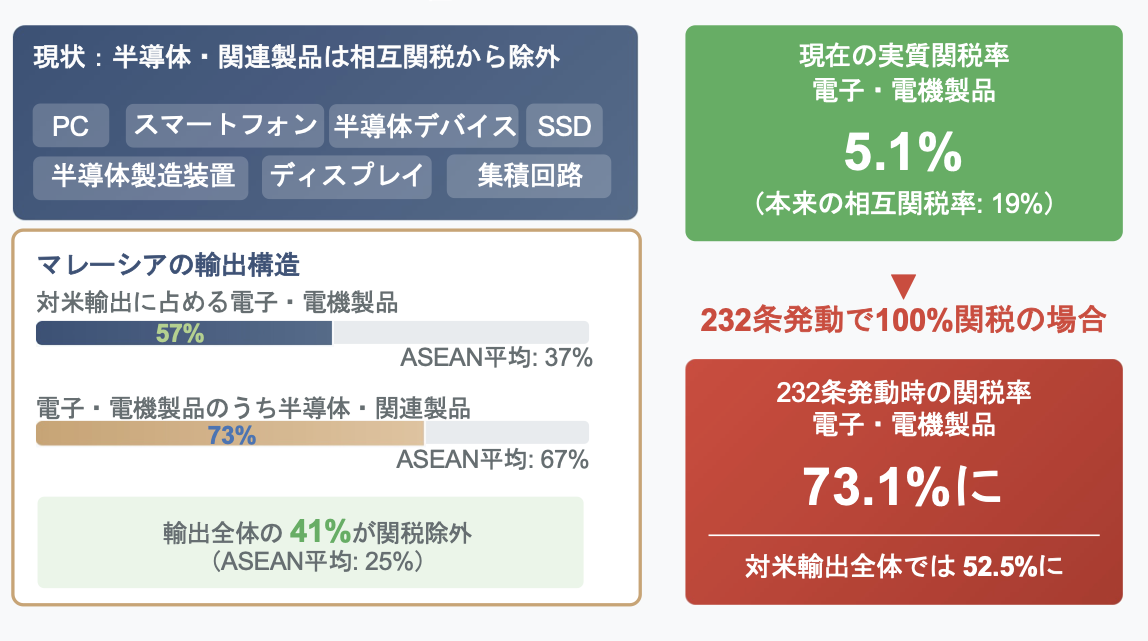第919回:善意を活かせない組織で、優秀な人ほど静かに去っていく ―あるボランティア経験者の体験談から考える、人の意欲を活かすマネジメント―
前回は、コロナ禍での若者のキャリア意識の変化についてでした。今回は、あるボランティア活動の体験談から、組織のあり方を考えてみます。
ある自治体の市民マラソン大会で、救護ボランティアに参加した方から印象的な話を聞きました。
事前に説明会があり、それぞれの役割も決まっていました。当日は自分の役割をしっかり果たそうと準備して臨んだそうです。しかし、現場ではボランティアを束ねるスタッフが、事前に決められていた役割を十分に尊重せず、その場の判断で次々と指示を変えていきました。
結果として、自分が本来担当するはずだった仕事はほとんどできず、何となくその場にいるだけで終わってしまったそうです。
「役に立ちたいと思って参加したのに、何もできなかったのが残念だった」
その方は、仕事や家事で忙しい中、時間を縫ってこのボランティアに参加していました。そして帰宅後、「自分を大切にできなくてごめんね」と、自分自身に言いたくなったそうです。
このような出来事は、ボランティアの現場で決して珍しいものではありません。そして、ボランティアの輪が、一部の熱意ある人を超えて広がらない一因になっている可能性があります。
同時に、この話は海外の日系企業の現場でよく聞かれる声とも重なります。
日系企業は一般に、組織への貢献意欲が強い人材が多いと言われます。しかし一方で、「役割が曖昧である」「その場の判断で指示が変わる」「誰が何を決めているのか分からない」といった状況が生じることがあります。
そのような環境では、問題意識を持ち、自分の役割を果たそうとする人ほど違和感を抱きます。そして、声に出して不満を言うのではなく、静かに組織を離れていきます。
重要なのは、人材の意欲そのものではなく、それを活かすための運営です。
役割が明確で、その役割が尊重されているとき、人は自律的に動き、期待以上の力を発揮します。逆に、役割が軽視されると、意欲の高い人ほど「ここでは自分の力は必要とされていない」と感じてしまいます。
人材が定着しない理由は、必ずしも待遇や能力の問題ではありません。善意や意欲を活かせるかどうかは、現場のマネジメントのあり方に大きく左右されます。
海外拠点において人材の力を最大限に引き出すために求められているのは、「優秀な人を採用すること」だけではなく、「その人が役割を果たせる環境を整えること」なのかもしれません。
そして、良い仕事をしたいという気持ちに共感し、それを汲み取るためには、マネジメントの側が外的な評価や金銭的対価ばかりに目を向けるのではなく、「良い仕事をしたい」という内側の動機そのものに向き合い、共感する姿勢が求められます。
ボランティアと企業組織。一見すると別の世界の話ですが、人の意欲を活かすという点では、驚くほど共通しているのです。
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |