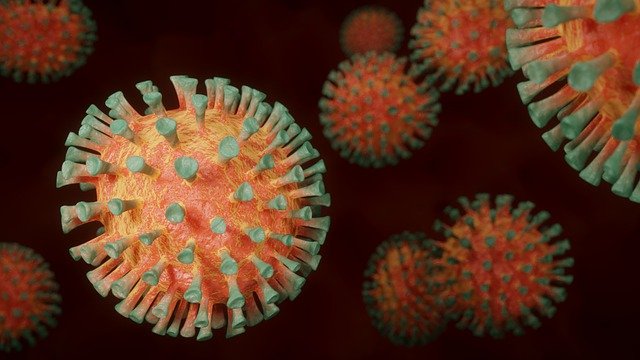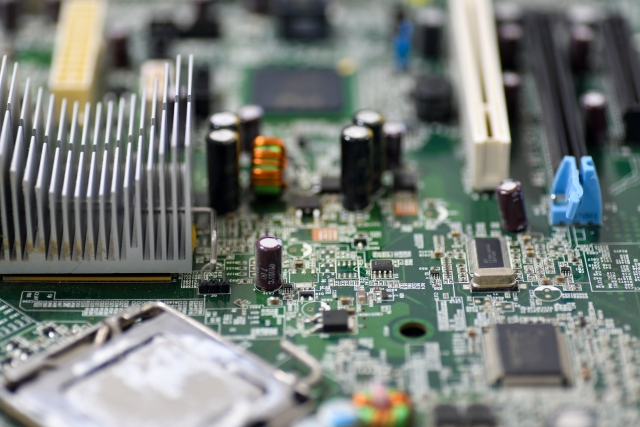第918回:不安な時代、人はまず何を求めるのか?
――コロナ禍で変わった若者のキャリア意識(後編)――
前回は、コロナ禍で若者のキャリア意識が変化し、その方向性が都市と地方で異なっていたことをご紹介しました。今回は、その変化がどのように行動や意欲につながっていたのかを見ていきます。
分析の結果、地方大学の学生では、「働く条件」を重視する意識が、「職場の人間関係を大切にしたい」という意識と結びつき、それが地元で働きたいという志向を後押ししていました。
つまり、安心できる条件があり、信頼できる人間関係が想像できるとき、人はその場所にとどまり、関わろうとするということです。
ただし、ここで一つ重要な点があります。人間関係を重視する意識は、それだけでは自己成長や挑戦意欲には直結していませんでした。鍵となっていたのは、「社会からどう評価される仕事か」「誰の役に立つのか」という社会的意義の感覚です。
データが示していたのは、
働く条件 → 人間関係 → 社会的意義 → 自己成長
という順序でした。
この結果は、企業の人材マネジメントにも示唆を与えます。不安定な環境下で、いきなり「挑戦しろ」「成長せよ」と求めても、人は動きません。
まず必要なのは、
・安心して働ける条件
・孤立しない人間関係
・自分の仕事が誰の役に立つのかという意味づけ
です。その土台があって初めて、内発的な意欲や挑戦が立ち上がります。
これは若手社員に限った話ではありません。変化の激しい時代において、勤労意欲を高める鍵は、能力や根性ではなく、順序にあるのかもしれません。
安心のあとに、意欲は生まれる。
その順序を無視しないことが、これからのマネジメントには求められているように思います。
調査にご協力くださった方々にこの場を借りて心より感謝申し上げます。
論文情報は以下。末尾のURLから全文をご覧いただけます。
Kokubun, K. (2025). During the COVID-19 Pandemic, the Gap in Career Awareness Between Urban and Rural Students Widened. Psychology International, 7(4), 103.
https://doi.org/10.3390/psycholint7040103
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |