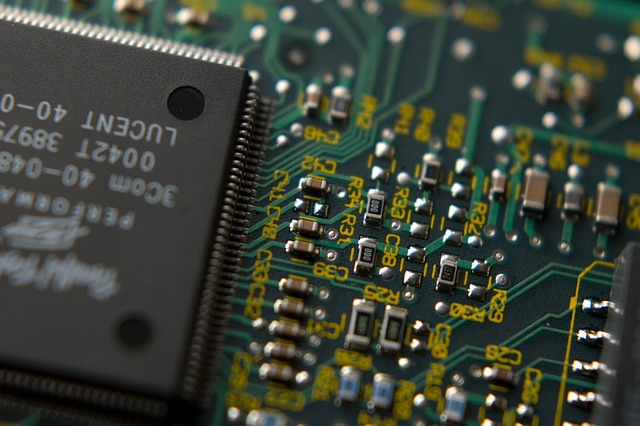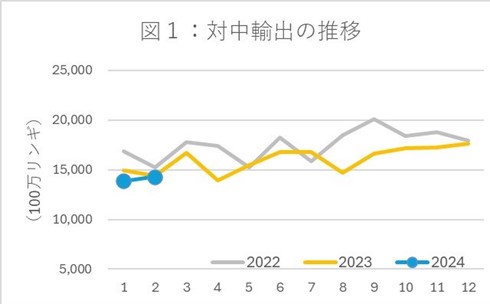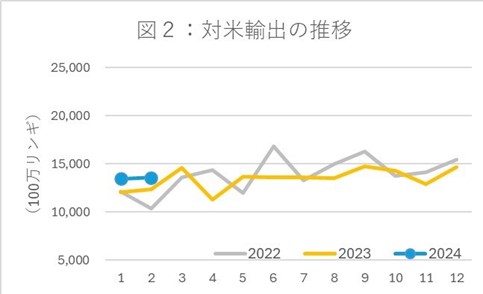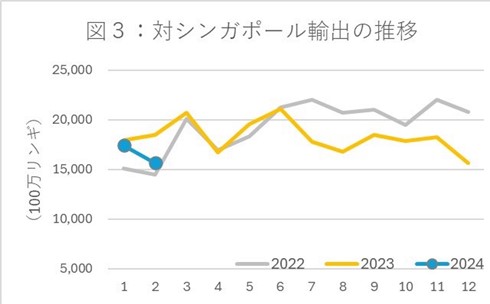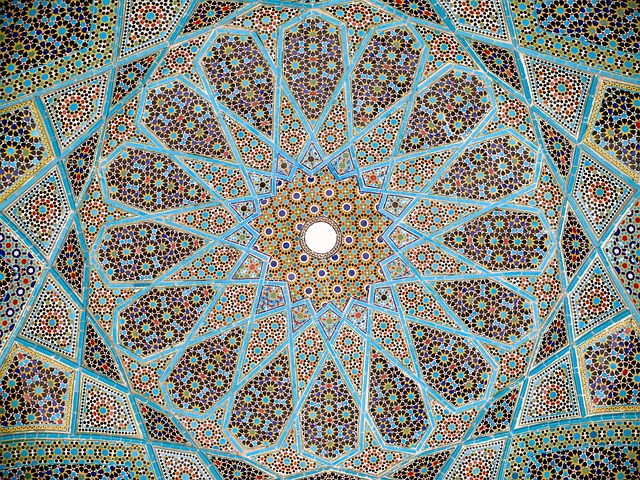半導体サプライチェーンにおけるマレーシアの存在
英語有力経済誌フィナンシャル・タイムズ電子版が3月11日に”Malaysia: the surprise winner from US-China chip wars”というタイトルの記事を配信しました。「米中半導体戦争での意外な勝利者はマレーシア」という趣旨です。同記事には米国への半導体輸出国について言及があり、2023年2月時点を示すグラフでマレーシアが20%を占めていることが示されました。2位は台湾15.1%、3位ベトナム11.6%、4位タイ8.7%、5位韓国7.5%であり、日本は7位で3.5%でした。中国は6位で4.6%となっていますが、今後、米中の半導体戦争が継続する限りは減っていく可能性が高そうです。
マレーシアは半導体サプライチェーンの一角を形成していましたが、今回のように米国という重要市場に対してマレーシアが1位となることは、記事タイトルのとおり「surprise」と言えそうです。もちろん、半導体関連といっても幅があります。先進国には、いわゆる「川上」にあたる半導体素材や「川中」の製造設計が集中します。半導体素材は日本や韓国が強く、設計は台湾STMCのような会社が強くなっています。マレーシアは「川下」に当たる半導体産業が殆どです。
このようにマレーシアでの半導体産業が盛り上がっている理由は、これまでに一定の理工系人材を育ててきたことや投資環境の良さ、そして、長年の半導体を含めた製造業の産業集積を経ているからです。人口が3,000万人の中規模であるため、インドネシアやベトナムといった億単位の人口のある国に比べると、目立ち難い存在と捉えられてしまいがちです。大手IT企業のマレーシアへの投資ニュースは、NDVIAを始めとして続いており、今後、半導体サプライチェーンにおけるマレーシアの役割がより高まっていきそうです。
※本連載の内容は著者の所属組織の見解を代表するものではなく、個人的な見解に基づくものです。
| 川端 隆史(かわばた たかし) マレーシア研究者。1976年栃木県生まれ。東京外国語大学マレーシア専攻卒業。1999 年から2010年まで外務省に勤務し、在マレーシア日本国大使館、 国際情報統括官組織などを歴任。2010年11月から15年7月までは SMBC日興証券でASEAN担当シニアエコノミスト。2015年8月に ソーシャルメディアNewsPicksと経済・産業情報プラットフォームSPEEDAを手がけるユーザベースに転身、2016年3月から同社シンガポール拠点に駐在。2020年12月から2023年3月まで米国リスクコンサルティングファームのクロールのシンガポール支社に勤務。共著書に「マハティール政権下のマレーシア」、「東南アジアのイスラーム」、「東南アジア文化辞典」がある。この記事のお問い合わせ は、takashi.kawabata★gmail.comまで(★を@に変更ください) |