【コタキナバル】 サバ州コタキナバルと連邦直轄地ラブアンを結ぶ旅客フェリーが、
同フェリーはジェセルトン・ポイント・
エコノミークラスの往復運賃は、マレーシア人が45リンギ、
コタキナバルから乗船する場合、利用者はジェッセルトン・
(マレー・メイル、5月27日)

【コタキナバル】 サバ州コタキナバルと連邦直轄地ラブアンを結ぶ旅客フェリーが、
同フェリーはジェセルトン・ポイント・
エコノミークラスの往復運賃は、マレーシア人が45リンギ、
コタキナバルから乗船する場合、利用者はジェッセルトン・
(マレー・メイル、5月27日)

【クアラルンプール】 米国がマレーシアに課すと宣言している24%「相互関税」
米国は2025年7月8日までの90日間を猶予期間とし、10%
マレーシアは関税引き下げについて米国と断続的に協議を続けてお
米国通商代表部(USTR)のデータによると、
(ブルームバーグ、ザ・スター電子版、エッジ、5月27日)

【クアラルンプール】 クアラルンプールで開催されていた東南アジア諸国連合(
今回のASEAN首脳会議では、2回目となるASEAN・
アンワル首相は「すでに我々には強固な連携がある一方で、
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、ザ・スター、ベルナマ通信、

【クアラルンプール】 ラフィジ・ラムリ経済相とニック・ナズミ・ニック・
ラフィジ氏は「
現職の副党首だったラフィジ氏は、党役員選でアンワル・
一方、ニック・ナズミ氏は、
現職のニック・ナズミ氏は、12人が出馬した党首補選(
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ザ・スター電子版、

【クアラルンプール】 2つ目の第5世代(5G)
契約では、
ファーミ・
1つ目の5G網は政府系デジタル・ナショナル(DNB)
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、ザ・スター電子版、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 ニトリホールディングス(本社・札幌市北区)は26日、
開業日は6月5日。同社にとってケダ州初進出となり、
ニトリグループの店舗としては1,037店舗目で、同社は「

【ペタリンジャヤ】 自動車販売会社、ナザ・イースタン・モーターズは、
連邦高速道路沿いの大規模自動車販売店、ナザ・
新ショールームのオープンに合わせて、
(ジグホイールズ、ポールタン、5月26日)

【クアラルンプール】 東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議が26日、
会議冒頭にアンワル・イブラヒム首相があいさつ。
クアラルンプール宣言は「ASEAN2045:
(マレーシアン・リザーブ、ベルナマ通信、5月26日)

【クアラルンプール】 マレーシアの財政赤字は3月末時点で219億リンギで、
歳入は3%増の721億リンギで、売上・サービス税(SST)
3月末時点の政府債務は国内総生産(GDP)比で62.6%
(エッジ、5月22日)
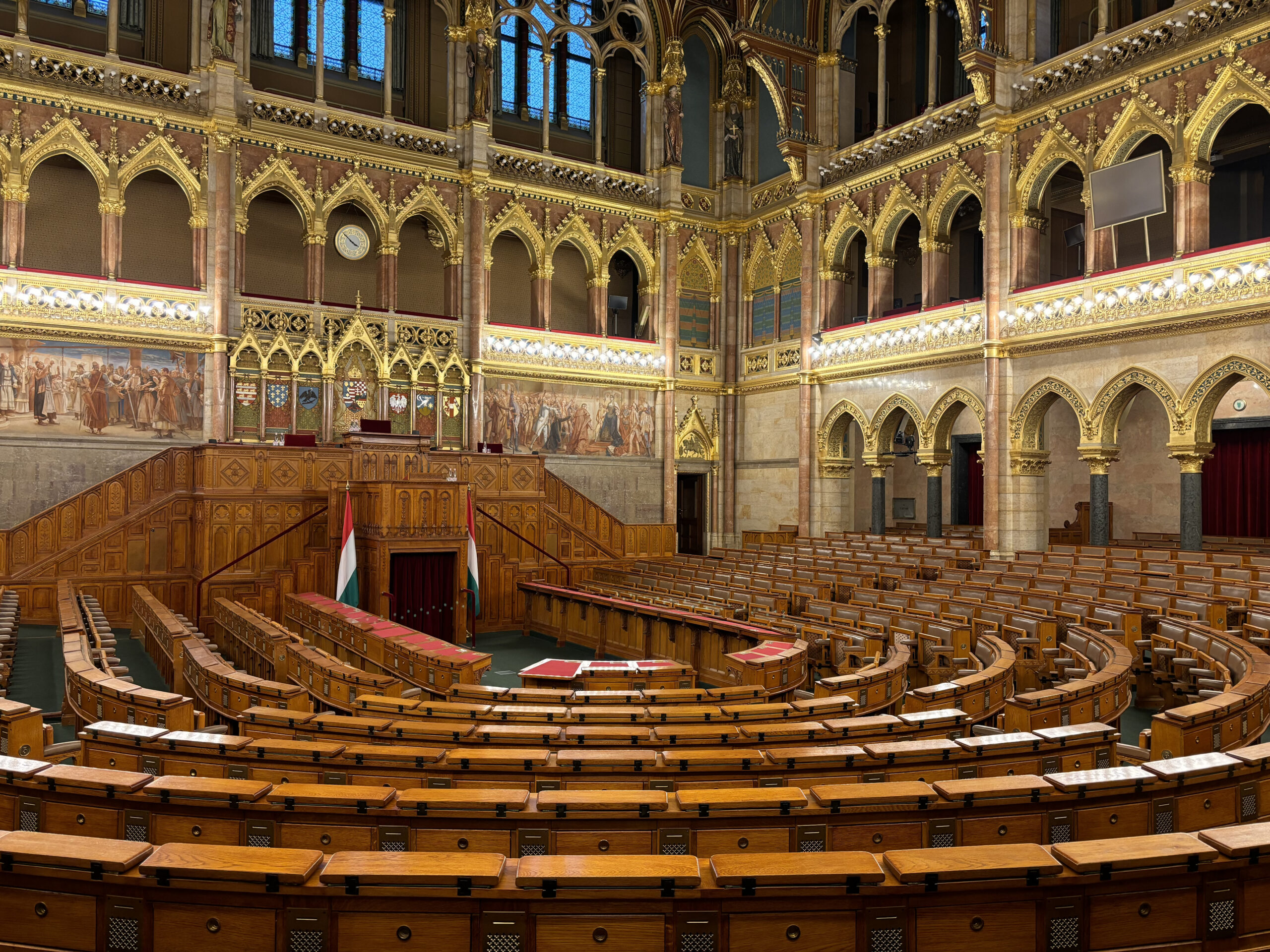
【クアラルンプール=アジアインフォネット】 与党連合・希望同盟(PH)の中核党・人民正義党(PKR)
12人が出馬した党首補選(定員4人)では、
青年部部長は現職のムハンマド・カミル・アブドル・