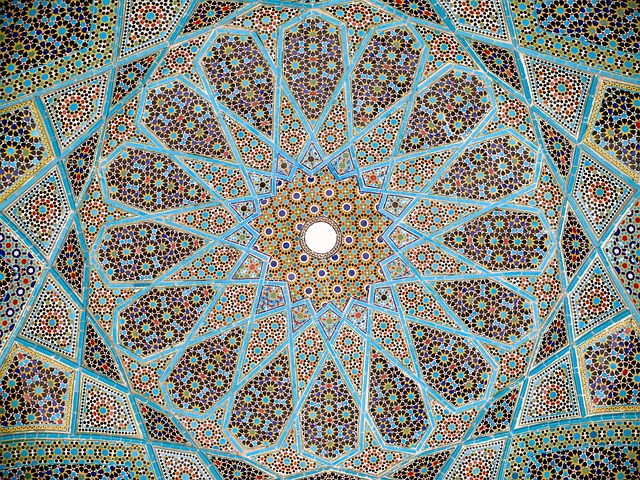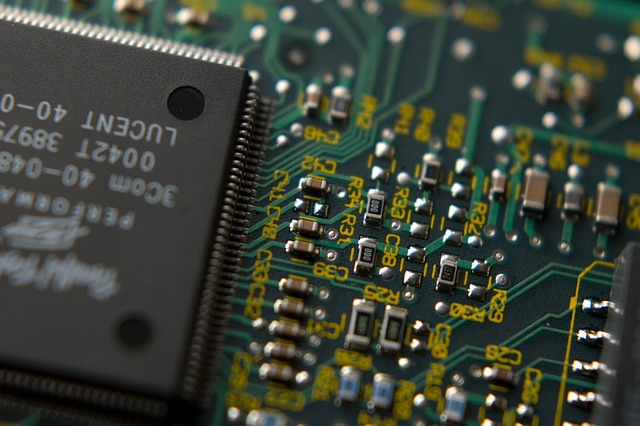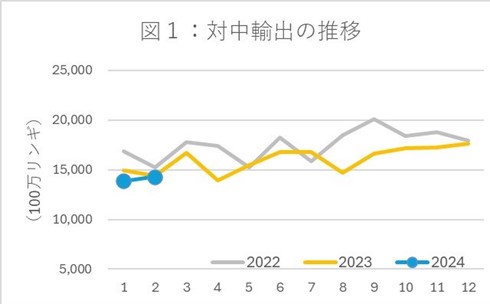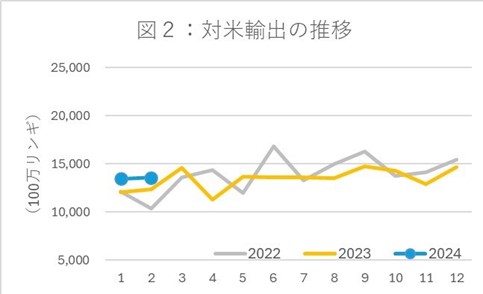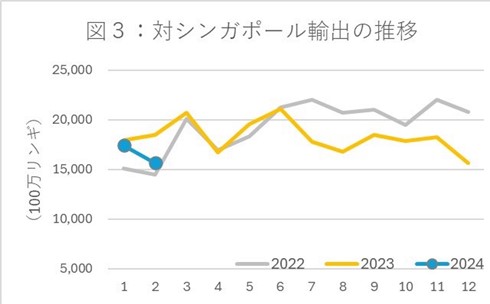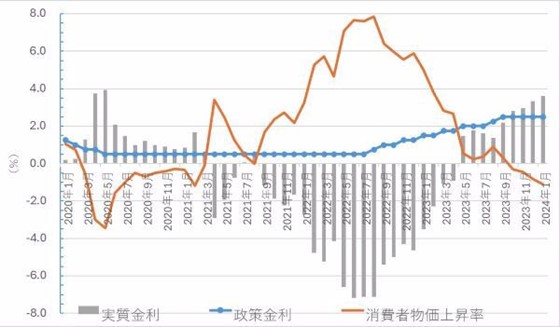第871回:ライフスタイルとモチベーション(11)駐在員にとって大事な睡眠と食事
前回は、良いライフスタイルを維持することで、健康が維持されるというお話でした。今回は、1月にマレーシアBIZナビ・ウィークリーの読者の皆さんに協力いただいたアンケート調査の結果の一部をご紹介します。
今回の研究では、ライフスタイルに関する7つの変数を盛り込みました。このうち、睡眠と食事が、文化的知性や心の知性を高めるうえで特に効果的であることが示されました。睡眠の質は、報酬の期待値と関連しています。そのため、睡眠不足の人は、そうしないことで得られる報酬を正しく評価できないことで、簡単に仕事を休んだり、予定や会議をキャンセルしたり、社会活動をサボったりしてしまいます(Palmer & Alfano, 2017)。こうした経験を繰り返す駐在員であれば、感情を利用したり、ストレスに耐えるような能力の不足を自覚したりしていても不思議ではありません。
また、食事のバランスは、認知やエピソード記憶と関連しています(Guasch‐Ferre & Willett, 2021)。エピソード記憶とは、時間や場所、そのときの感情を含むイベントの記憶のことです。そのため、食生活の不健康な人が、異文化体験やその時の感情の具体的な記憶が曖昧になり易く、そのことで、異文化についての知識や興味が下がり、また交流の際に適切な行動を取ることを苦手と感じていても不思議ではありません。
一方、運動は、今回の研究では文化的知性や心の知性との相関が見られませんでした。運動は、自制心や向社会的行動、対人コミュニケーションなどにポジティブな効果があること、また、個人で行うよりもチームで行うほうが効果が大きいことなどが、システマティックレビューで確かめられています(Teixeira et al., 2012)。しかし、しばしば差別を受けた少数民族が民族的な誇りを取り戻すためにスポーツチームに参加するように(Thorpe et al., 2014)、現地に馴染めない駐在員が日本人駐在員主催のスポーツコミュニティに参加し、そのことで、チーム内の団結心の向上と引き換えに、現地の文化への興味や、文化を相対的に見るためのメタ認知の発達を遅らせている可能性も考えられます。こうしたメリットとデメリットが打ち消し合うことで、サンプル全体としては文化的知性や心の知性との相関が確認できなかったのかも知れません。
現地との交流の妨げにならない限り、健康なライフスタイルは脳の働きを高め、現地経営に良い影響を与えます。皆さんも心がけてみてはいかがでしょうか。
Guasch‐Ferre, M., & Willett, W. C. (2021). The Mediterranean diet and health: A comprehensive overview. Journal of internal medicine, 290(3), 549-566. https://doi.org/10.1111/joim.13333
Palmer, C. A., & Alfano, C. A. (2017). Sleep and emotion regulation: An organizing, integrative review. Sleep medicine reviews, 31, 6-16. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2015.12.006
Teixeira, P. J., Carraca, E. V., Markland, D., Silva, M. N., & Ryan, R. M. (2012). Exercise, physical activity, and self-determination theory: a systematic review. International journal of behavioral nutrition and physical activity, 9, 1-30. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02264-8
Thorpe, A., Anders, W., & Rowley, K. (2014). The community network: an Aboriginal community football club bringing people together. Australian journal of primary health, 20(4), 356-364. https://doi.org/10.1071/PY14051
國分圭介(こくぶん・けいすけ)
京都大学経営管理大学院特定准教授、東北大学客員准教授、国際経済労働研究所理事、東京大学博士(農学)、専門社会調査士。アジアで10年以上に亘って日系企業で働く現地従業員向けの意識調査を行った経験を活かし、産業創出学の構築に向けた研究に従事している。
この記事のお問い合わせは、kokubun.keisuke.6x★kyoto-u.jp(★を@に変更ください) |