【クアラルンプール=アジアインフォネット】 外食大手のサイゼリヤ(本社・埼玉県吉川市)は19日、
マレーシア法人の名称は、マレーシアサイゼリヤとなる見通し。
サイゼリヤは中国、香港、台湾に法人を設立しており、

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 外食大手のサイゼリヤ(本社・埼玉県吉川市)は19日、
マレーシア法人の名称は、マレーシアサイゼリヤとなる見通し。
サイゼリヤは中国、香港、台湾に法人を設立しており、

【クアラルンプール】 通信事業者のマキシスは、チャイナ・モバイル・
両社は昨年8月、5G(第5世代移動通信)
MVNOは自社で通信設備を持たず、
CMリンクでは、
(ビジネス・トゥデー、エッジ、報道資料、8月18日)

【クアラルンプール】 国内2つ目の5G(第5世代移動通信)ネットワーク業者、
ウーン・ウーイユエン最高技術責任者(CTO)は開始式で「
ベルジャヤ・タイムズ・スクエアでの開始式では、
(ベルナマ通信、ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、エッジ、

【セパン】 空港運営会社マレーシア・エアポーツ・ホールディングス(
メガット氏によると、外国航空会社12社のうち、
中国市場については、
新航空会社を探す一方で、既存の航空会社とは、増便や、
さらにKLIAの第3ターミナル建設については、
また航空貨物でも国際宅配大手のDHL、フェデックス・
(ニュー・ストレーツ・タイムズ、8月18日)

【クアラルンプール=アジアインフォネット】 統計局によると、
モノの貿易収支の黒字が前期の384億9,
第一次所得収支の赤字は前期の171億3,
金融収支の赤字は前期の203億1,

【プトラジャヤ】 マレーシア・イスラム開発局(JAKIM)のシラジュディン・
ソーシャルメディアで拡散している問題の動画は「
シラジュディン氏は、「
(ザ・サン、ビジネス・トゥデー、ベルナマ通信、8月15日)
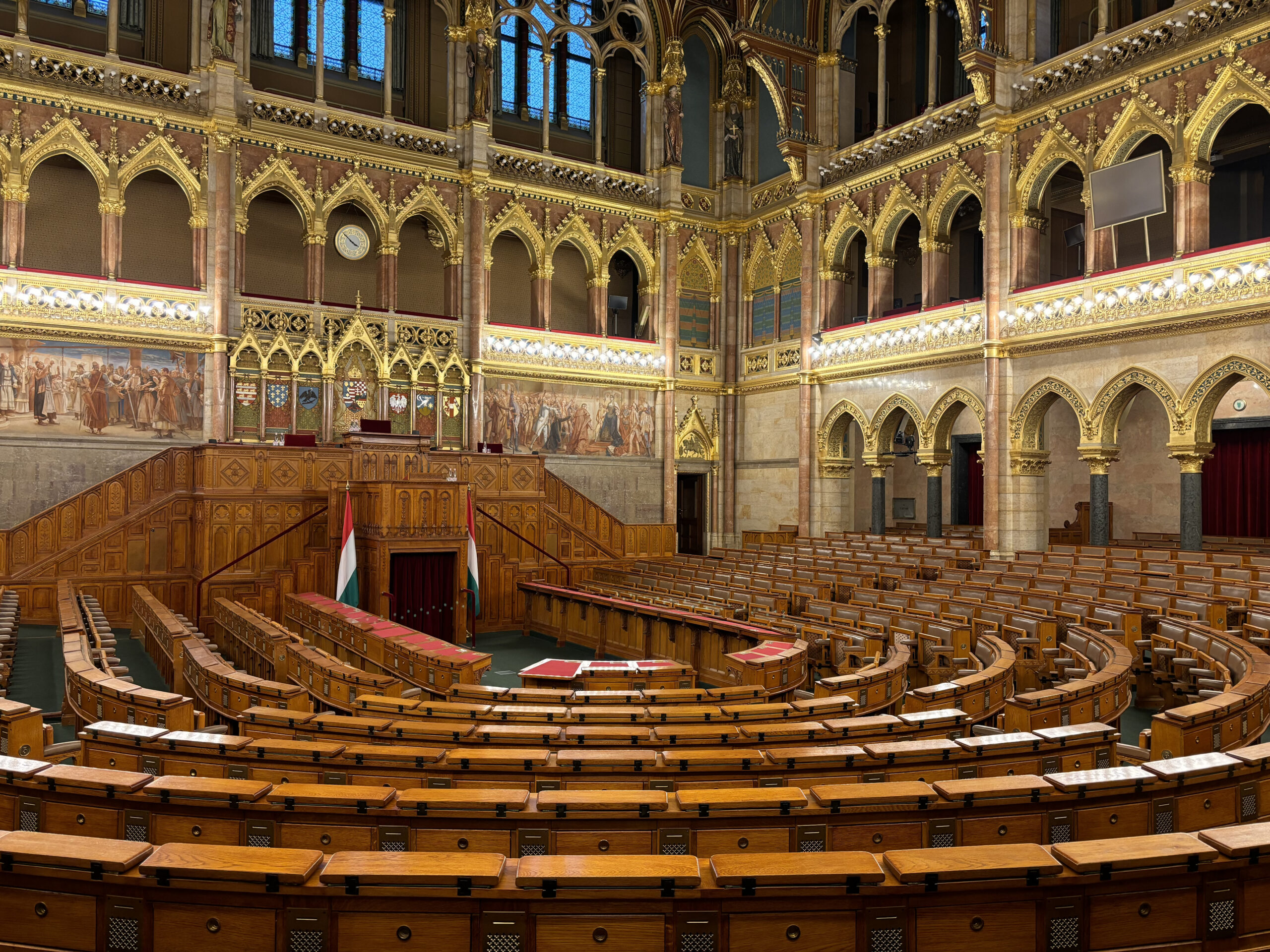
【クアラルンプール】 アンワル・イブラヒム政権に協力する国民戦線(BN)
アンワル政権内における冷遇に対する不満やBNの中核である統一
2022年総選挙では、
PH構成党から選出された華人閣僚は複数いるが、インド・
政治アナリストらはMCAとMICが揃ってBNを離脱した場合、
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、フリー・マレーシア・

【クアラルンプール】 セパン・インターナショナル・サーキット(SIC)のアザン・
セパンでF1レースが初めて開催されたのは1999年で、
シャフリマン氏は、
その上でSICが現在、
シャフリマン氏はさらに、
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、8月16日)


第906回:中小企業の両利き経営(9)デジタル化、 グリーンイノベーションと持続可能性
前回は、デジタル化が、時間、資金、人材といったリソースが少ない中小企業が外部知識を獲得し、知識基盤を強化するのに役立つというお話でした。経営者と従業員がデジタル化に向けた意思統一をすることが、その後の両利き経営やデジタル能力の向上、さらにはイノベーションのために不可欠といえます。
さらに、デジタル技術の活用は企業の持続可能性を向上させる可能性があります。中小企業は世界の産業汚染の60~70%を占めているにもかかわらず、大企業に比べて環境意識が低く、環境技術や法律に関する知識が不足しているとされています。しかしながら、ステークホルダーからの圧力や、環境意識の向上を求める消費者の需要の高まりに後押しされて、中小企業はグリーンイノベーションに取り組むことが多いようです。この時、企業は、デジタルツールを使用することで、資源の使用状況をリアルタイムで監視し、プロセスを最適化し、廃棄物を削減し、環境効率を向上させることができます。例えば、ブロックチェーンはリサイクル原材料が使用されていることを証明するために使用されています。したがって、デジタル化は、資源利用の最適化、循環型経済および持続可能なビジネスモデルの実装を促進することで、環境パフォーマンスを向上させることができます。
しかし、中小企業はデジタルプラットフォームの導入において、必要なリソース、スキル、コミットメントが不足しているなど、特有の課題に直面しています。そのため、人的ネットワークは重要なリソース源となり、中小企業が貴重な機会を発見するのに役立ちます。例えば、使用済み、リサイクル、回収された材料からなる生産投入物を取り扱い、それを顧客価値に変換するプロセスを設計するには、材料の継続的な循環と廃棄物の削減・排除という観点から、材料の利点と限界を理解しているパートナー、専門家、顧客の関与が必要です。
Kokubun, K. (2025). Digitalization, Open Innovation, Ambidexterity, and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Narrative Review and New Perspectives. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202504.0009.v1
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |


第905回:中小企業の両利き経営(8)両利きとデジタル化
前回は、グリーンイノベーションについてでした。両利きは持続可能性にプラスの影響を与え、それが新製品の成功とグリーンイノベーションにプラスの影響を与える可能性があります。しかし、グリーンイノベーションの導入には、オープンイノベーションと同様にコストがかかります。
コスト削減戦略の最も重要な方法の一つがデジタル化です。デジタル化は、時間、資金、人材といったリソースが少ない中小企業が外部知識を獲得し、知識基盤を強化するのに役立ちます。漸進的イノベーションと比較して、より高度なイノベーション型である急進的イノベーションは、より多くの暗黙知と外部の異種リソースを必要とし、企業の既存の知識基盤をはるかに超える可能性があります。この場合、デジタル化は中小企業に、市場で入手可能な情報を選別し、業界の最先端を見極める貴重な機会を提供します。これにより、中小企業はより積極的に急進的イノベーションを実施できるようになります。さらに、パートナーと動的な情報や知識を共有することで、新たなアイデアやコンテンツが生まれ、企業のイノベーション・パフォーマンスの向上につながります。
さらに、限られたリソースしか持たない中小企業はリスク許容度が低く、漸進的イノベーションに比べて不確実性とリスクが大きい急進的イノベーションを避けるインセンティブが生じます。デジタル化は、企業が不確実性を発見、特定、回避し、リスクの程度を軽減するのに役立ちます。その結果、中小企業が急進的イノベーションを実行することが促進されます。
ドイツの様々な業種の中小企業1,474社を対象とした研究とフィンランドの中小企業204社を対象とした研究の結果は、組織の両利き性がデジタル志向と成長戦略の関係を媒介することを示しました。これらは、両利き性はデジタル化を伴う場合、より高いパフォーマンスにつながる可能性が高いことを示唆しています。しかし、デジタル化と両利き性の順序は逆になることもあります。イスタンブールの中小企業366社を対象とした研究では、デジタル変革が中小企業の両利き性と競争優位性の関係を部分的に媒介していることが示されました。同様に、2019年の世界銀行ビジネスサーベイと、2020年と2021年に21か国の8,928社を対象に実施された追跡調査を使用した研究では、組織の両利き性がデジタル能力を通じて間接的にイノベーションに影響を与えることが示されています。これらの調査結果は、組織の両利き性がデジタル能力を強化することで、企業の競争優位性を高めることができることを示唆しています。以上の一連の研究は、デジタル「志向」(すなわち、デジタル化へのコミットメント)が両利きを予測する可能性があり、両利きがデジタル「変革」とデジタル「能力」を予測する可能性があることが示されています。
これらの研究は、両利きの組織がいつ、どのようにデジタル化を導入すべきかについて重要な示唆を与えてくれます。すなわち、経営者と従業員がデジタル化に向けた意思統一をすることが、その後の両利き経営やデジタル能力の向上、さらにはイノベーションのために不可欠といえます。
Kokubun, K. (2025). Digitalization, Open Innovation, Ambidexterity, and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Narrative Review and New Perspectives. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202504.0009.v1
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |