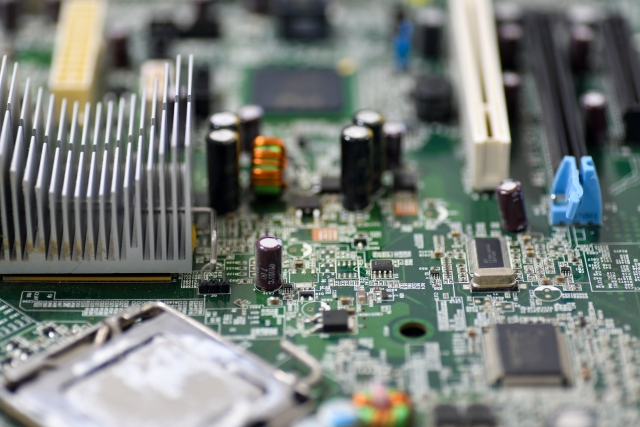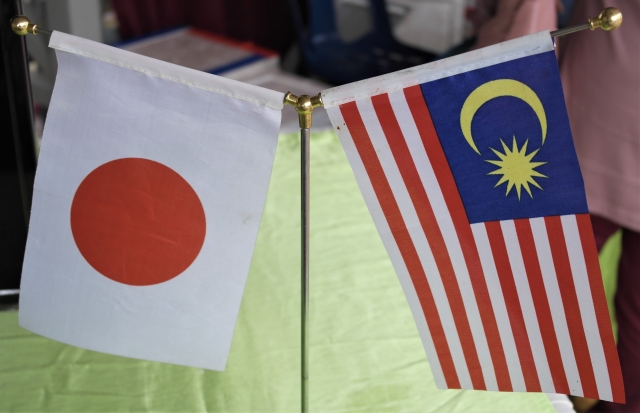第910回:中小企業の両利き経営(13)デジタル化はいつ導入すべきか?
前回は、グリーン・イノベーションとオープン・イノベーションの関係についてでした。両者が相互に強化し合う正のフィードバック・ループを形成することで、企業の両利き能力や持続可能性が高まることが期待できます。
今回は、中小企業におけるデジタル化の導入意義とその時期についてです。両利き経営は、中小企業の環境負荷低減を目的としたグリーン・イノベーションやサステナビリティへの取り組みと関連し、特に長期的視点からその重要性が高まります。資源に制約のある中小企業は、オープン・イノベーションを通じて両利き経営を実現できますが、コストが高いため、デジタル化によって低コスト化を図る必要があります。また、そのためには人材や資金ネットワークの支援が欠かせません。
中小企業は依然としてデジタル技術の導入に慎重であり、投資不足や不確実性が障壁となっています。しかし、デジタル・プラットフォームの能力を高めることで、成長を促す可能性があります。特にデジタル化とオープン・イノベーションを統合し、両利き経営を促進できれば、グリーン・イノベーションと企業業績の向上を同時に実現でき可能性があります。日本では多くの中小企業が脱炭素化に取り組んでいますが、人材や知見の不足、排出量の可視化の困難さなどが障害となっています。デジタル化はこれらの課題を解決し、内部資源の効率化や外部資源の活用を通じてグリーン・イノベーションを推進する有効な手段になり得ます。
また、デジタル化は企業間や大学などとの連携を強化し、オープン・イノベーションの成果を高める可能性があります。そのためにはAIなどのデジタル技術に精通した人材の確保が必要であり、政策的支援も重要です。両利き経営はすべての企業に適するわけではありませんが、将来志向的な戦略として有効であり、国家や社会全体の持続可能性に貢献する可能性があります。
Kokubun, K. (2025). Ambidextrous SMEs for a sustainable society. A narrative review considering digitalization, open innovation, human resources and green innovation. Next Research, 100839. https://kwnsfk27.r.eu-west-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fauthors.elsevier.com%2Fa%2F1lqFZArcH5v%257EhR/1/010201997bdd92dc-2f55d85f-3f6a-4e09-a50f-d2029cba34fb-000000/-j2abMH3tXcKZD4AoMaphgExEJk=445
| 國分圭介(こくぶん・けいすけ) 京都大学経営管理大学院特定准教授、 |